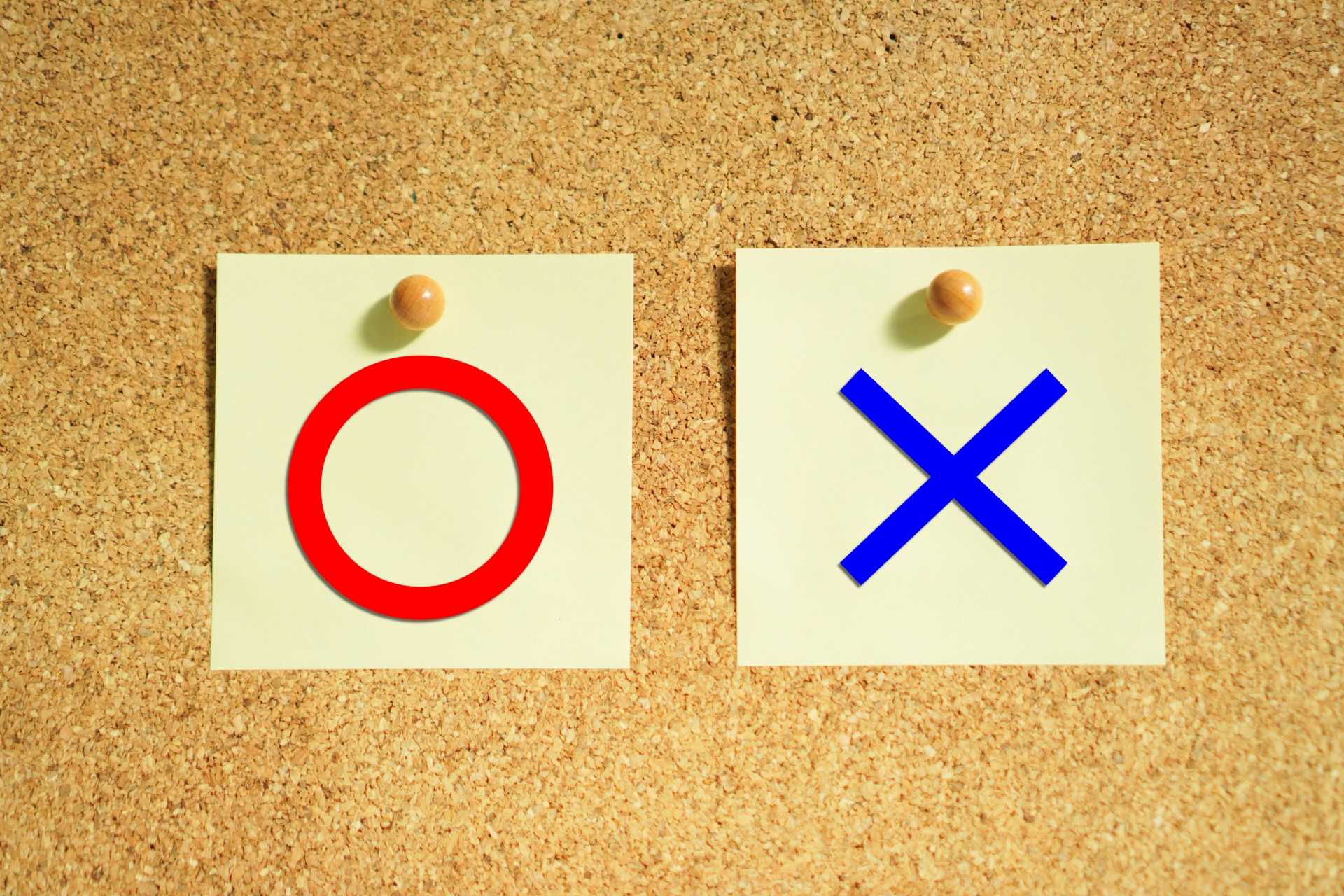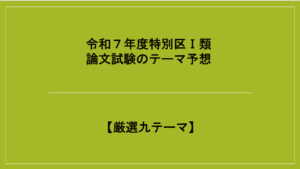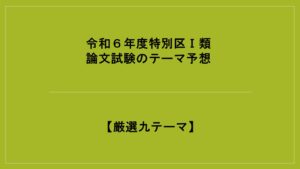特別区Ⅰ類の第一次試験は、専門試験(多肢選択式)、教養試験(多肢選択式)及び論文試験の3種目によって構成されています。また、それぞれの配点や合格最低点が一切ブラックボックス化されており、この点で国家系の採用試験とは異なっています。
特別区Ⅰ類の第一次試験においては筆記試験(専門・教養)と併せて論文試験の点数を加味して合否が決定されるため、一義的なボーダーというものは存在しません。
しかし、受験者からの報告に基づくと、おおむね安心できるラインがどこにあるかといった傾向は掴むことは可能です。
この記事では、独自に受験者からの報告を調査、集計した結果に基づき、大まかなボーダーの目安をお伝えします。
受験者の筆記試験点数と一次試験合否(集計)
第一次試験の受験者からの報告に基づく筆記試験の点数と一次試験合否(最終合否ではないため注意)は以下のとおりです。
なお、筆記試験点数については専門試験と教養試験の点数を合算していますので、満点が80点ということになります。
| 特別区Ⅰ類第一次試験(事務)における受験者の筆記試験点数と合否結果 | |||
| 筆記試験 点数(点) | 一次試験 合格率 | (合格人数 /報告人数) | (不合格人数 /報告人数) |
| 30点以下 | 8% | 1/13 | 12/13 |
| 31~32点 | 20% | 1/5 | 4/5 |
| 33~34点 | 25% | 2/8 | 6/8 |
| 35~36点 | 27% | 3/11 | 8/11 |
| 37~38点 | 47% | 9/19 | 10/19 |
| 39~40点 | 50% | 9/18 | 9/18 |
| 41~42点 | 48% | 13/27 | 14/27 |
| 43~44点 | 56% | 14/25 | 11/25 |
| 45~46点 | 64% | 14/22 | 8/22 |
| 47~48点 | 64% | 9/14 | 5/14 |
| 49~50点 | 68% | 13/19 | 6/19 |
| 51~52点 | 71% | 10/14 | 4/14 |
| 53~54点 | 81% | 13/16 | 3/16 |
| 55~56点 | 63% | 5/8 | 3/8 |
| 57~58点 | 80% | 8/10 | 2/10 |
| 59~60点 | 100% | 6/6 | 0/6 |
| 61~62点 | 50% | 2/4 | 2/4 |
| 63~64点 | 80% | 4/5 | 1/5 |
| 65点以上 | 78% | 7/9 | 2/9 |
ただし、これらは私が受験者から直接受けた報告のほか、LINEオープンチャット、SNS等の情報を基にしています。個人の自己申告に準拠する情報ですので、虚偽であったり、採点の誤りがある可能性も否定できません。(特に30点以下から1名の合格報告がある点は懐疑的です。)
参考程度に留めていただく必要はありますが、それでも十分に価値のあるものだと考えます。
なお、詳細は集計基準は以下のとおりですので、気になる方はご覧ください。
集計基準(押すと開きます。)
- 2020~2024年度本試験のデータを基に集計
- 「筆記試験点数」は専門試験と教養試験の点数を合算したもの
- 「論文試験は白紙で提出した」等の場合でも、筆記試験を受験した場合であれば集計に含める。
- 事務験種は、「特別区Ⅰ類」試験のうち、「事務」のもののみを集計
合格率が5割を超えるのは筆記試験が80点中45点程度か
それでは、以上のデータを考察していきます。このデータから得られる含意は次の3点だと考えます。
- 合格率が5割を超えてくる素点合計点数は45点程度
以上のデータから、「45~46点」の受験者を見ると、22人中14人が合格しており、単純に算出すると63%が合格しています。
しかし、こういったデータの特性として、「結果が良かった人ほど回答率が高い」というものがあります。実際にはこれくらいの得点で不合格者となっている方はもう少し多いと推察されます。その割引分も加味して、合格率が5割を超えてくる素点合計点数は、概ね45点程度(得点率にして6割弱)と言えるのではないでしょうか。
ただし、試験実施年度による難易度の差も影響してきます。特に近年の特別区Ⅰ類では易化が顕著です。
- 素点合計点数が65点以上の超高得点でも不合格となる場合もある
公務員試験において、素点合計点数が65点(得点率にして8割強)程度であれば、まず間違いなく筆記試験は合格できます。しかし、こと特別区Ⅰ類に限っては、論文を加味して採点されるため、筆記試験が8割程度の超高得点であったとしても不合格となる場合もあります。ここから、特別区Ⅰ類の第一次試験における種目ごとの配点は公開されていませんが、論文試験の配点が大きいことが分かりますし、あるいは論文試験に足切りが設けられている可能性が示唆されます。
- 素点合計が30点程度の低得点でも合格できる場合もある
これも国家系との大きな違いですが、素点合計が30点程度だったとしても、論文試験の出来で逆転が可能です。国家一般職等では、筆記試験の素点が極端に低ければまずそこで第一次試験の合否判定が行われるため最終合格を手にすることは不可能ですが、特別区Ⅰ類の場合ではその限りではありません。
注目すべきは「33~34点」の層でも4人に1人が第一次試験を突破していることで、33点というと得点率にして約4割に相当します。ある程度の倍率が発生する試験種であるにもかかわらず、論文の出来次第では、筆記試験が4割の得点率でも最終合格できる可能性が0ではないというのが、特別区Ⅰ類の特徴です。
また特別区Ⅰ類のトレンドとして、ここ数年は倍率が顕著に低下しています。
5〜10年前は、最終合格のための実質倍率が5〜10倍程度でしたが、今は2〜3倍程度となっています。そういったトレンドの最中にあり、ボーダーは年々低下傾向にあると見ています。
勉強期間が長い人や予備校活用者の点数が高め
また、上掲のデータでは、可能な限り勉強期間や予備校の活用有無等についても確認を行っていました。
この記事では詳述しませんが、勉強期間が長い人、特に1年程度の時間をかけてきた人の得点が明らかに高いという結果でした(80点中60点以上の点数を獲得している人のうち、過半数近くが1年以上勉強をしてきた人でした)。
また、アガルートアカデミーの「教養+専門型ワイド・スタンダード対策カリキュラム」を始め、何等かの公務員試験の総合的な講座を受講している人の得点率も高い傾向にありました。
改めて、論文試験の重要性が分かる結果に
以上の結果から読み取れることは、改めて、特別区Ⅰ類の一次試験においては、論文試験のウェイトが高いと推察できるということです。実際の論文試験のウェイトは公表されていませんが、80点中の30点強、つまり4割の得点率でも、論文試験の出来がよければ逆転できるのが特別区Ⅰ類の試験です。
翻って言うと、筆記試験で7~8割の高得点を取ったとしても、論文試験の出来が悪ければ不合格になり得るのが怖いところです。
特別区Ⅰ類の志望度が高い場合、必ずアガルートアカデミーの論文対策講座等のオンラインスクールで論文試験の講座を受けておくことが重要です。
アガルートアカデミーの公務員試験講座では、論文対策講座のみを単発で受講することも可能なので、特別区の本試験の直前に、プラスアルファ的に受講しておくことを推奨します。
また、本サイトでも、以下のような記事を作成していますので、よろしければご覧ください。