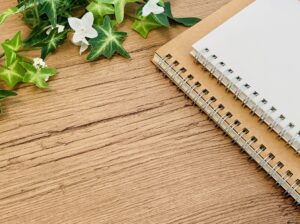この記事では、行政系の公務員(国家公務員・地方公務員)から民間へ転職する場合におすすめの業界・職種と、気を付けることについてお伝えします。
官民の人材の流動化
公務員の魅力や公務員試験のノウハウを発信するのがこのサイトの主旨ですが、私は、公務員として働き続けることだけが正しいキャリアパスだとは考えておりません。
現に、公務員を退職したのち、別の業界で活躍している知人は多いですし、私自身も、公務員を退職した後に民間企業での勤務経験があります。
特に国家公務員総合職等は激務で知られていますし、公務員の中には生涯働き続けるのが難しいような現場もあります。
生活あっての仕事ですので、ワークライフバランスを含め、ご自身のライフスタイルに合った環境を求めて職を変えるというのはごく自然なことだと考えられますし、筆者は転職について肯定的に考えています。
おすすめの民間の転職先
それでは、本題に入ります。公務員から民間へ転職する場合の、おすすめの業界・職種についてお話します。
コンサル
まずは、コンサルティングの業界です。野村総研のような大手日系や、アクセンチュアのような外資系に限らず、日系中小のコンサルでも公務員から転職の実績は多いです。
ただ、気を付けたいのは、コンサル業界内の全ての会社において公務員が重宝されるかと言われれば、そうではありません。1、2年くらいの公務の実務経験があれば、業界内でも、公共サービスのコンサル事業を取り扱っているところにおいて、公務員は重宝されることが多いです。
特に国家公務員総合職(又はⅠ種)からの転職は多いです。ただ、民間企業からすれば国家公務員一般職(Ⅱ種)との違いはあまり意識されず、組織名で評価されることが多いです。たとえば国家一般職で厚生局に採用された場合でも厚生労働省の職員としてみなされることが多いので、転職において不利になることはあまり無い印象です。
また、都道府長や市区町村の職員であっても、十分にコンサル業界への転職の可能性があります。大手コンサル会社でも、地方自治体をクライアントとしているところが多いからです。
いずれにせよ、自身の業務を転職時の面接において説明できるようにしておくことは重要です。
公務員試験の面接試験が特殊であることと同じように、コンサル業界への転職の面接についてもまた特殊な準備を要します。手っ取り早いのは、転職活動のエージェントを活用することです。
コンサルを志望する場合も含め、28歳くらいまでの方の転職活動の場合であれば、第二新卒の転職に特化している【第二新卒エージェントneo】が最もおすすめです。
また、コンサルへ転職する場合のメリットとして、給与が挙げられます。地方公務員や地方勤務の国家公務員であれば30歳時点での年収は500~600万円程度です。
公務員の最高峰である国家公務員総合職でさえ、30歳時点での年収は高くとも800万円程度です。(公務員の年収は以下の記事に詳しいです。)一方、コンサルであれば最大手であれば1000万円を上回ることもありますし、中小でも700~800万を狙えます。

独立行政法人
続いて、独立行政法人です。
半公務員と呼ばれることもあるくらいですので、公務員の仕事と重なる部分は大きいです。
独立行政法人通則法上の独立行政法人は、全て何等かの省庁が監督を行う立場にあります。たとえば、国際協力機構(JICA)であれば外務省が、情報処理推進機構(IPA)であれば経済産業省大臣が監督を行っています。
国家公務員の場合、所属する省庁が管轄する独立行政法人への転職を希望する場合、言うまでもなくその経験が重宝されることになります。そもそも、出向といった形でこれらの独立行政法人で働くこともあり得ます。
独立行政法人は、あまり知られていないかもしれませんが、多くの場合は独自に新規採用や中途採用を行っているところがほとんどですので、転職先として一考に値します。たとえば、以下のような独立行政法人は職員規模も多く、転職できる可能性が高いです。
- 国際協力機構(JICA)
- 都市再生機構(UR都市機構)
- 住宅金融支援機構
- 国立病院機構
- 地域医療機能推進機構
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
国家公務員でなければ転職が難しいということもありません。たとえば、以上のように医療系・福祉系の独立行政法人も多いですので、地方公務員の場合でも経験を活かすことのできる場所も多いです。
なお、独立行政法人の中には、ごくまれに、国家公務員一般職試験の枠組みによって採用者を賄っているところがあります。国立印刷局と造幣局が該当します。これ以外の独立行政法人は、民間企業と同じように、面接試験をベースとした独自の採用試験を行っているところがほとんどです。
なお、給与については公務員と同等水準です。
政府系金融機関
次いで、政府系金融機関です。公共性の高い金融機関であるため、公務員の業務と重なり合う部分もあります。地方自治体であれば中小企業支援や産業施策に携わったことのある経験があれば評価されることは必至です。国家公務員であれば、財務省、金融庁、経産省等での勤務経験があれば特に高く評価されます。
そもそも政府系金融機関とは何かということですが、主には以下のものを想定しています。
- 日本政策金融公庫(JFC)
- 商工組合中央金庫 (商工中金)
- 日本政策投資銀行(DBJ)
- 国際協力銀行 (JBIC)
以上のうち、日本政策金融公庫と商工中金は規模もかなり大きく、国家公務員・地方公務員問わず転職できる可能性は高いです。また、組織の規模が大きいため、日本中で働く機会を得られます。
一方、日本政策投資銀行は高度な専門性を求められ、かなり採用難易度が高いです。東大生始め日本最高峰レベルの人材が志望してくるところです。
給与については、日本政策投資銀行と国際協力銀行は極めて高い水準です。商工中金も公務員よりはやや高いくらいの水準です。日本政策金融公庫は公務員と同程度の給与水準です。
その他政府系機関
そのほかの政府系機関においても、公務員の業務との親和性の高いものがあります。たとえば大量採用を行っている日本年金機構は、自治体で年金の業務を扱っていた人にとっては転職先としてよい選択肢となります。
行政書士法人、司法書士法人、法律事務所
続いて、士業系の事務所についてもおすすめできます。行政書士法人、司法書士法人、法律事務所等です。
特に行政書士は公務員からの転身先として狙い目です。国家公務員・地方公務員問わずおすすめできます。もし法務局や出入国在留管理庁、国税関係の勤務経験があれば更におすすめできます。
行政書士資格は、公務員を長く(17年ほど)続けても得ることはできますが、公務員試験の合格者であれば、そこそこ勉強すれば独力で取得することは可能です。
たとえば、スタディングの行政書士講座は働きながらでもスキマ時間に勉強して合格することを前提としているため、現職の公務員の方にもおすすめです。更に、行政書士法人(行政書士事務所)で暫く経験を積んだ後、独立開業を目指すことも可能です。
行政書士の業務として思い浮かぶのは、会社設立、事業許可、財産移転関係の業務ですが、これらについて直接の業務の経験はなくとも、公務員であれば法令に基づいて仕事を行う素地(リーガルマインド)がおのずと身についていることが多いため、行政書士等の業務とも親和性が高いです。
また、行政書士事務所によっては、行政書士資格を持っていない人でもOKな求人を出しているところもあるので、そういったところでアシスタントとして実務をこなしつつ、資格勉強をするという選択肢もあります。
同様に司法書士についてもおすすめできますが、周知のとおり行政書士の上位互換ともみなされることのある資格ですので難易度は高いです。
働きながらスタディングの司法書士講座で勉強して合格を目指すことも可能と思われますが、狭き門です。(かくいう筆者も司法書士資格は持っておりません。)
法律事務所についても、法科大学院を経由せずに司法試験に合格するのは現実味がないですが、資格を問わず求人を行っている法律事務所もありますので、転職先として一考の価値があります。
SE
最後に、意外に思われるかもしれませんが、昨今ではSE等のエンジニアもおすすめできます。
私の知り合いの中にも、行政系(文系)の国家公務員や地方公務員から未経験でエンジニアに転身したという方は何名かいらっしゃいます。プログラミング言語も「言語」に変わりないので、法令を読める人間であれば、ある程度SEの現場においても持っている思考力の融通が利くといった話もあります。
実力主義の世界なので、それを受け入れられるかどうかは十分に検討しておいたほうが良いです。勉強が好きで、かつ成果主義の働き方を望む場合にはよい転職先となります。
民間企業のSEに転身する場合は、転職先の会社によってその業務は完全に異なるため、転職エージェントに相談しながら検討していくことが重要です。28歳くらいまでの方であれば、第二新卒の転職活動に特化している【第二新卒エージェントneo】が最もおすすめです。