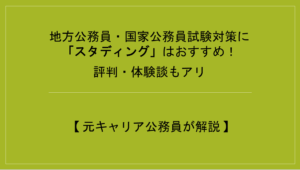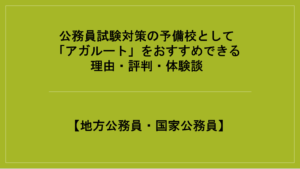昨今の報道では、公務員試験の人気や難易度が凋落しているという話をしばしば目にします。
この記事では、その実態を明らかにすべく、勤務地が主に関東圏となる大規模な試験種の試験倍率の近年の推移を調査し、時系列に沿ってまとめましたので、ご覧ください。
首都圏の公務員試験の倍率の推移
結果は以下のとおりです。なお、これらの試験倍率は、基本的に「1次試験受験者を最終合格者で除した値」としていますが、「申込者を合格者で除した値」しか公表されていない場合は、その値を採用しています。
地方公務員(大卒・行政系区分)
まずは首都圏の主な地方公務員の試験として、特別区Ⅰ類、東京都Ⅰ類B、横浜市、川崎市、神奈川県、千葉県の大卒区分の倍率を一覧化しました。例えば特別区Ⅰ類ではSPI枠が導入されている年度もありますが、このような場合、法学や経済学等の択一筆記試験が課せられる試験種の倍率を掲載しています(母数が大きいからです。)。
※もちろん、AIに自動収集させたデータではなく、筆者が各自治体等のサイトにおいて一次情報を自力でピックアップしたものです。
| 試験実施年度 | 特別区Ⅰ類 (事務) | 東京都Ⅰ類B (行政 一般) | 横浜市 大卒 (事務) | 川崎市 大卒 (行政 事務) | 神奈川県 1種 (行政) | 千葉県 上級 (行政A) |
| R7 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 3.4 | 2.8 |
| R6 | 2.3 | 1.5 | 4.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 |
| R5 | 2.5 | 2.4 | 8.1 | 4.1 | 3.2 | 3.6 |
| R4 | 3.6 | 3.1 | 6.1 | 5.9 | 4 | 4.2 |
| R3 | 4.8 | 13.7 | 5.2 | 3.3 | 5.5 | 5.4 |
| R2 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.3 | 3.2 | 3.6 |
| R1 | 5.7 | 5.6 | 4.2 | 4.9 | 4 | 6.5 |
| H30 | 5.4 | 6.1 | 5.3 | 6.2 | 6 | 6,5 |
結果は以上のとおりです。全体的に易化傾向にあることが読み取れますが、特に都庁(東京都)と特別区ではその傾向が著しいように思えます。
国家公務員(大卒・行政系区分)
続いて、国家公務員についてです。ここでは、主なものとして国家総合職(法律及び経済区分)、国家一般職(行政関東甲信越)、国税専門官、財務専門官、裁判所事務官(一般大卒東京管区)を取り上げます。
| 試験実施年度 | 国家総合職 (大卒 法律) | 国家総合職 (大卒 経済) | 国家一般職 (行政 関東) | 国税専門官 (A区分) | 財務専門官 | 裁事一般職 (大卒 東京) |
| R7 | 19.1 | 7.0 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 3.6 |
| R6 | 20.9 | 6.4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 3.2 |
| R5 | 18 | 5.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.9 |
| R4 | 17.1 | 6.8 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 4.9 |
| R3 | 15.7 | 6 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 8.1 |
| R2 | 8.6 | 4.5 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 2 |
| R1 | 17 | 8.6 | 4 | 3.0 | 3.3 | 6.1 |
| H30 | 18.1 | 8.5 | 4.9 | 3.4 | 3.9 | 6.6 |
こちらも、地方公務員と同様に、その変化はややマイルドであるものの、全体的にはやや易化傾向にあることが見て取れます。
ちなみに、国家一般職等では全国で地域別に採用を行っていますが、関東甲信越の場合は、他の地域よりもやや倍率は高め程度です。このことは以下の記事に詳しいです。

総評
いかがでしょうか。まず注意していただきたいのは、令和2年度の倍率が全体的に低下しているのが見て取れます(特に国家総合職や裁判所事務官等)。ただし、これはコロナショックによるものですので、異常値として捉えるべきです。令和2年度を度外視して見てみると、たしかに近年の公務員試験の倍率は低下の一途を辿っており、難易度についてもおおむね同じことが言えそうです。
特別区Ⅰ類、政令市(川崎市)、県庁、国家総合職、国家一般職、裁判所事務官等はその傾向が顕著であると思います。特に、特別区Ⅰ類は私が受験生だった頃は6〜8倍のイメージで、何ならそれ以前は10倍を超えていたこともありました。それを考えると物凄い勢いで易化が進んでいると思います。
政策立案や行政の執行に携わる公務員の人材確保が危ぶまれていることは、個人的には大きな問題であると考えています。
現に。国家公務員の場合であれば、人事院は、試験受験資格の拡大、試験科目の緩和等、毎年さまざまな手を打っています。地方公務員の場合においても、筆記試験を行わない試験種を新設するなどの対応を急いでいるところも目立ちます。
一方、これから公務員を志す人の立場からすれば、この状況はチャンスとも考えられます。
注意事項
「倍率=難易度」ではないので注意
なお、以上のとおり各試験種の倍率を掲載しましたが、これが一義的にその難易度を示すものではないことにはご注意ください。公務員試験の「倍率」と「難易度」は完全にイコールではありません。「難易度」に対して因果関係を持つ因子には、「倍率」のほかに「受験者のレベル」があるためです。例えば東大の学部入試でも、多くの学部において前期日程の倍率は2〜3倍台です。上の例で言えば、令和5年度の国家総合職(大卒経済)と東京都Ⅰ類Bでは後者の方が倍率が高いですが、難易度としては前者の方が高いと推察します。
近年の公務員試験は、倍率だけ見ると数倍程度のものも多く、見かけ上は簡単に見えますが、倍率の低いこれらの試験では多数の専門試験が課されるため、いずれにせよ対策に大きな時間をかけなければならないことに変わりはありません。
公務員試験の対策に必要な時間は、難易度の凋落に伴って小さくなってきているのは間違いないですが、安定して全ての試験種に合格できる学力を身につけるためには、1,000時間程度が必要だと考えています。このことは以下の記事でも触れています。

倍率が低くても公務員試験対策は必須
倍率だけとってみれば簡単のように思えますが、実際には、公務員試験のために準備してきた人たちの中でこの倍率を競うことになるので、ある程度難関な試験であることに変わりありません。
たとえば、以上の試験種を志望する場合、「アガルートアカデミー」や「スタディング」といったオンラインスクール等で各科目の講座を受講した上、過去問集で対策を積んでおくことは必須です。特に東京都(都庁)Ⅰ類の志望度が高い場合は、アガルートアカデミーには「教養+都庁速習カリキュラム」という都庁に特化したカリキュラムがあるため強く推奨できます。
また、可能であれば、アガルートアカデミーの面接対策講座は受講しておきたいです。この講座は模擬面接も含めて実施することが可能ですが、特に公務員の面接については、客観的な目線で見なければ気づけないことも多いです。
同様に、特別区Ⅰ類の志望度が高い場合は教養論文対策講座を受講しておきたいです。単科的に、全国のどこからでも受講することが可能です。
国家総合職、国家一般職には、更に官庁訪問が課される
また、国家総合職と国家一般職については、上掲の表において、最終合格までの倍率を掲載しています。実際にはその後に行われる官庁訪問においてもある程度の倍率が生じています。
官庁訪問の倍率はブラックボックス化されており不詳ですが、単純に最終合格者と実際の採用者数の関係から推測するならば、官庁訪問期間中フルに訪問して内定をどこかから得られる倍率は2〜3倍程度と思われます。
上掲の表の値に、さらに官庁訪問の倍率を掛け合わせた値が、内定を得るための実質的な倍率になるということです。現在でも、大卒法律区分から人気の府省庁等を目指す場合、実質的な倍率は100倍近くなることもあり得ます。
まとめ
- 全体の傾向として、公務員試験の倍率は低下傾向にある。
- 特別区Ⅰ類、一部の政令市、一部の県庁、国家総合職、国家一般職、裁判所事務官等は特に著しく低下している。
- ただし、公務員試験において倍率と難易度は同一の概念ではないため要注意。
公務員試験の試験種別の難易度については、以下の記事でまとめていますので、よろしければご覧ください。