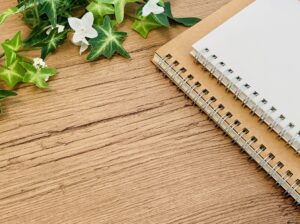この記事では、少し雑談めいたトピックですが、新卒でこれから公務員になる方や、若手の公務員に向けて、おすすめの賃貸物件の条件をお話しします。
なお、国家公務員と地方公務員のいずれも対象として記事を執筆しております。
そのほか、既にこのサイトで作成した以下の記事とも関連しますので、よろしければ合わせてご覧ください。


それでは、ここから本題に移ります。
家具・家電付きの物件
まず、個人的におすすめしたいのは、家具・家電付きの物件です。
特に、国家公務員や都道府県の公務員である場合、採用されて数年で転居を伴う異動が発生することも想定されるため、荷物を身軽にしておくことが得策です。
もちろん、転居の際に自前の家具・家電を持ち運ぶことも不可能ではありませんが、大型の家具・家電は引越し代が手痛いという事情もあります。
また、公務員であれば基本的には長く勤め続けることを前提にしている人も多いはずです。
市区町村の公務員の場合は基本的に転居を伴うような異動が発生することは無いはずですが、このようにライフプランが立てやすいため、同棲や結婚といったライフステージの変化の際に、パートナーが既に家具・家電を持っていた場合、自前の家具・家電が不要(無駄)になってしまうおそれもあります。
具体的には、もし東京近郊に住まう場合は、「クロスワンルーム」で家具・家電付き物件を探すことがおすすめです。家具・家電付きの物件は多数ありますが、その中でも、仲介手数料も抑えられるというということも加味して、最もおすすめできます。
地方に住まう場合は、「レオパレス21」を推奨できます。こちらも、家具・家電物件を取り扱っていることはもちろん、仲介手数料が安く済むというメリットがあります。
住居手当と相性が良い物件
続いて、住居手当が満額でもらえるところを選ぶことが重要です。
地方公務員の場合
住居手当の制度は自治体によって異なることが多いですが、ここで、大阪市の事例を参照します。
大阪市の場合、住居手当の金額や支給要件は、「職員の給与に関する条例」第11条の3に定められています。
職員の給与に関する条例(大阪市:昭和31年9月30日条例第29号)
(住居手当)
第11条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。ただし、市規則で定める職員については、この限りでない。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額10,000円を超える家賃を支払つている職員
(2) (略)
2 住居手当の月額は、28,000円(前項第1号に掲げる職員のうち同項第2号に掲げる職員でもあるものにあつては、その額に2分の3を乗じて得た額)を超えない範囲内において、同項各号に掲げる職員の区分に応じて市規則で定める。
3 大阪市内の住宅に居住する職員に対する前項の規定の適用については、同項中「28,000円」とあるのは「30,500円」とする。
大阪市:条例・規則など
これを読み解くと、以下のことが言えます。
- 大阪市職員の場合、自ら賃貸住宅を契約して、月額10,000円以上を超える家賃を払っている職員等に対して、住居手当として月額28,000円を支給する。
- ただし、大阪市内の住宅に居住する職員の場合、住居手当として30,500円を支給する。
住居手当の支給要件や、区域内に住まう場合の加算の有無等は自治体によって異なりますので、物件探しを始める前に、採用される自治体の給与条例をネットで確認しておくことがベターです。
自治体によっては、区域内に住んでも加算が無いというところもあるので、事前に把握しておくことをおすすめします。
国家公務員の場合
国家公務員の場合、住居手当の主たる規定は、「一般職の給与に関する法律」(昭和25年法律第95号)第11条の10に置かれています。この条文を引用します。
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
(住居手当)
第十一条の十 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
二 (略)
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
ロ 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
二 (略)e-Gov 法令検索:一般職の職員の給与に関する法律
3 (略)
少し読みにくい作りになっていますが、以上をまとめると以下のようになります。
- 国家公務員の場合、自ら月額16,000円を超える賃貸住宅を契約している職員に、住居手当を支給する。
- その金額は、借り受けている賃貸住宅の金額によって異なるが、家賃の月額が61,000円以上の場合、限度額である28,000円を住居手当として支給する。
条文が読みにくいですが、国家公務員の場合、家賃に応じて住居手当の月額が変わってきますので、「住居手当が満額もらえる金額の物件に住んだ方が得である」という考え方も可能です。
基本的には、支払う家賃の金額が大きいほど、住居手当の金額も大きくなりますが、簡単に一覧化すると、次のようになります。
| 支払う家賃の金額 | 住居手当の金額 |
| 16,000円 | 0円 |
| 20,000円 | 4,000円 |
| 25,000円 | 9,000円 |
| 30,000円 | 12,500円 |
| 35,000円 | 15,000円 |
| 40,000円 | 17,500円 |
| 45,000円 | 20,000円 |
| 50,000円 | 22,500円 |
| 55,000円 | 25,000円 |
| 60,000円 | 27,500円 |
| 61,000円以上 | 28,000円(上限) |
(ちなみに、狭義の「家賃」、すなわち賃料のことであり、共益費は含まないためご注意ください。)
このように、知らない場合は損をしてしまうおそれがあるのが住居手当の制度なのです。
公務員の住居手当の制度については、以下の記事でもう少し詳しく述べていますので、よろしければご覧ください。

市区町村職員の場合、職住近接であること
ここは人によっても意見が分かれますが、個人的には、市区町村の地方公務員の場合、職住近接をおすすめします。
何より、勤務地がほぼ固定されているという強みを最大限に活かすことができます。
 山島
山島私も、東京都特別区の職員だった頃は、職場から自転車で10分で通えるところに住んでいましたが、ものすごく快適でした。
一方で、職場の近くに住んだ場合に気を付けたいのは、自治体が主催する地域の行事に参加しなければならない可能性があるということです。たとえば、土日に実際される総合防災訓練等がこれに当たります。休日はプライベートに徹したいという人にとってはデメリットにもなり得ます。
また、自治体区域内で災害が発生したり、そのリスクが高まった場合にも、出動しなければならないこともあります。筆者も、大型の台風が接近した際に、休日の夜から翌朝までにかけて避難所の設営に従事していたことがあります。
災害リスクが低い物件であること
これは公務員に関わらずですが、災害リスクが低い物件を選んだ方がよいのは言うまでもありません。
ただ、災害リスクが低い物件をどのようにして選ぶかといった基準については知られていないこともあるため、少しだけ触れておきます。
築浅であること
基本的には、木材や鉄骨、鉄筋は老朽化するため、築浅であるほど望ましいです。
特に目安となるのは、おおむね1981年より後に建築された物件であることが重要です。1981年に建築基準法が改正され、耐震基準がより厳しく見直されているからです。
地盤が強固であること
物件自体の条件も重要ですが、物件が建てられる場所の状態も重要です。
地盤(微地形区分)には種類があります。揺れにくい山地や台地に対して、三角州や海岸低地、後背湿地等は比較的揺れやすい地盤です。
これについては、国立研究開発法人防災科学技術研究所による「地震ハザードカルテ」で、事前に検索しておくとベストです。特定の地点において、10年以内に震度7の揺れが発生する確率等、様々なことを調べることができます。
一方、ネットの固定回線は基本的に不要
最後に、家選びに当たって「気にしなくてもいいこと」もあります。たとえば、インターネットの固定回線を引けることや、固定回線が無料で使えることをアピールしている物件もありますが、個人的にこれらは不要だと考えます。
オンラインゲームが趣味で、公務員として採用されてからも土日はハイスペック環境でゲームに没頭したいという方を除き、公務員の一般的な生活をする限り、Wi-Fiのモバイルルーターが1台あれば十分暮らしていけるからです。
推奨できるのは、BIGLOBE WiMAX +5Gのような、5Gの高速回線できるプランを利用できるものです。5Gの使用できる機種であれば、機能自体には大差がないため、BIGLOBEのようにコストを抑えて導入できるものが望ましいです。