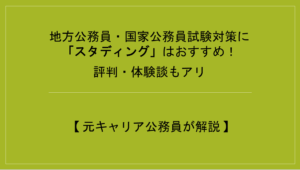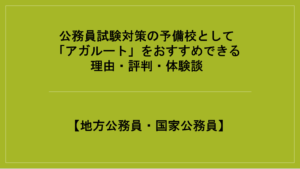この記事では、東京都(都庁)のうち、Ⅰ類の一般方式に合格するための方法を記述します。
試験区分の解説
本題に入る前に、東京都の職員採用試験の試験区分について、念のため概略を説明します。
Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類とは?
東京都の試験区分には、Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類の区分があります。ざっくりいうと、大卒の場合はⅠ類を受験することになります。この3つのうちではⅠ類が圧倒的に採用者のボリュームが大きいです。
Ⅱ類は栄養士等の限定的な試験区分で、Ⅲ類は主に高卒者を対象とした試験です。
Ⅰ類AとⅠ類B
また、Ⅰ類については、Ⅰ類AとⅠ類Bに分かれます。受験資格の対象年齢が、わずかにⅠ類Aの方が高くなっています。
基本的には、大学を卒業した方を対象として想定しているのがⅠ類A、大学院を修了した方を対象として想定しているのがⅠ類Bです。ただし、Ⅰ類Aは大学院修了が必須要件になっているわけではないので、年齢要件を満たしていればどちらの区分で受験しても可能です。
ただし、例年二つの区分の倍率が異なっているため、自身に有利な方を選ぶのが基本戦略です。
ボリューム的には、Ⅰ類Bの採用者数が圧倒的に多いです。
一般方式と新方式
最後に、一般方式と新方式の違いがあります。
名前のとおり、昔から続いてきた、法学・経済学等の専門試験等が課される方式が一般方式であるのに対して、新方式とは、いわゆるSPI等の簡易的なテストで試験を行うものです。採用のボリューム的には一般方式が圧倒的に多いです。
- 一般方式:筆記試験として法学・経済学等の専門試験や、数的処理等の教養試験が課される。採用枠は大きい。勉強すれば合格水準に達することが可能。
- 新方式:筆記試験はSPIによって行われる。採用枠は一般方式より小さい。勉強が努力に結びつきづらいが、逆にいうと無対策でも合格することも可能。
以上のような違いがありますが、どうしても都庁職員になりたい場合は、一般方式で受験すべきです。
東京都の試験は独特で難しいですが、努力すれば着実に合格に近づくことができるからです。一方の新方式は、民間就活組が併願で受けることを想定されており、運の要素も少し絡みます。
近年の倍率
東京都の採用試験は、とにかく採用倍率にムラがあることで知られています。
近年は極めて易化傾向であり、倍率が1倍台ということもあります。一方、かつては10倍を超えるような時もありました。東京都Ⅰ類Bの倍率の推移については、以下の記事で触れておりますのでよろしければご覧ください。

易化傾向にあることは間違いありませんが、依然として、難関試験であることには違いありません。詳しくは後述しますが、東京都Ⅰ類の試験問題は公務員試験の中でも独特であり、「潰しが利かない」という特徴があります。
東京都の試験に特化した対策をしておく必要があるため、見かけの倍率以上の難しさがあります。
東京都Ⅰ類の試験の特殊性
東京都Ⅰ類の試験の特殊性は、なんといっても筆記試験にあります。
公務員試験の筆記試験では、多くの場合、教養試験(数的処理や文章理解等)と専門試験(法学・経済学等)のいずれも多肢選択式、すなわちマークシート式で行われます。
一方、東京都Ⅰ類の専門試験は、記述式で行われるという特徴があります。
具体的には、出題される10題のうちから、任意の3第を選んで回答するというものです。たとえば最も受験者の多い行政(文系)の区分では、以下の10科目から1題ずつ、計10第が出題されます。
- 憲法
- 行政法
- 民法
- 経済学
- 財政学
- 政治学
- 行政学
- 社会学
- 会計学
- 経営学
専門記述式試験の対策
対策方法
以上の特殊性から、東京都Ⅰ類の試験は、国家公務員一般職や地方上級、市役所、裁判所事務官といった、主要な他の公務員試験との併願が可能であるものの少し困難となっています。
国家公務員一般職や地方上級の受験生であっても、憲法、民法、行政法、ミクロ経済学、マクロ経済学等の専門科目を勉強することになります。
しかし、多肢選択式と記述式の試験は性質が大きく異なるため、一般的な公務員試験の勉強にくわえて、記述式に特化した勉強が必要になります。
一般的な公務員試験の専門試験の多肢選択式試験では、ある程度同じ問題が使いまわされることもあり、とにかく「暗記」という作業を繰り返すことが必要です。一方で、記述式試験では、「暗記」のみならず「理解」まで求められるというのが最大の違いです。
具体的にどのように勉強するかについては、一つの答えとしては、一般的な公務員試験の専門試験に加えて、記述式試験対策用の問題集(テキスト)を追加でこなすという手段があります。
ただ、最も望ましいのは、最初から東京都Ⅰ類の専門記述試験対策に特化した講座を受講して勉強するということです。具体的には、アガルートの「教養+都庁速習カリキュラム」を受講することです。
あるいは、既に独学や、一般的な予備校の講座を受講済みの方であっても、東京都Ⅰ類の志望度が高めである場合には、アガルートの「教養+都庁速習カリキュラム」を受講して専門記述対策を強化しておくことを推奨します。
このサイトは、基本的に、「公務員試験は独学でも突破可能だが、できれば予備校やオンラインスクールを活用した方がよい」というスタンスをとってきました。しかし、こと東京都Ⅰ類に限っては、その原則は適用されないと考えています。それくらい、東京都Ⅰ類の専門記述試験は特殊性が高いからです。
専門記述試験における知識の仕入れ方、解法の導き方についてはコツがあるため、それを押さえた上で、各科目を理解する必要があります。「暗記」ではなく「理解」が求められるという特性上、独学ではなく他者から教わる方が効率的です。
東京都に限ると、科目間にコスパの差がある
続いて、ワンポイントアドバイス的なお話ですが、東京都Ⅰ類の試験は、科目間のコスパの乖離が大きいです。
たとえば行政の区分では、上掲の10科目が出題されますが、東京都Ⅰ類の専門記述試験に限ると、コスパに優れるのは次の科目です。
- 憲法
- 財政学
- 政治学
- 行政学
これらの科目は、既にスー過去や「解きまくり」に手をつけた方なら分かるかと思いますが、出題範囲や必要な暗記量は小さいです。一方で、東京都の専門記述試験では等しく1題分として出題されるため、コスパに優れるといえます。
一方で、行政の区分のうち、以下の科目はややコスパが悪いです。
- 民法
- 経済学
民法は出題範囲が大きいことから、公務員試験において、多くの場合「民法Ⅰ(総則・物権等)」と「民法Ⅱ(債権等)」の二科目分として出題されます。国家一般職、特別区Ⅰ類等では、民法の出題数は憲法の2倍と捉えることもできます。
しかしながら、東京都の専門記述では、単に「民法」と等しく1題分で出題されるため、ややコスパが悪いといえます。経済学についても、「マクロ経済学」と「ミクロ経済学」を合わせて「経済学」の1題分で出題されているため、コスパが劣ります。
もっとも、民法や経済学は他の公務員試験でも出題されることが多いため、既にほかの試験種のために勉強しているというも多いと思われます。
その場合は、引き続き民法や経済学で東京都Ⅰ類の専門記述試験を勝負するというのは良い戦略ですが、ゼロベースで東京都Ⅰ類に特化した対策を行いたい場合は、民法や経済学のコスパは悪いと言わざるを得ないです。
科目数は余裕を持って準備しておく
また、科目数については、余裕を持って準備しておくことが重要です。
出題される全ての科目について対策するのは無理ですが、最低限の3科目のみを対策して本試験に臨むのばギャンブルになってしまいます。東京都Ⅰ類の出題は空振りが生じる可能性も高いので、バッファとして、4~5題分以上はカバーできるようにしておきたいです。