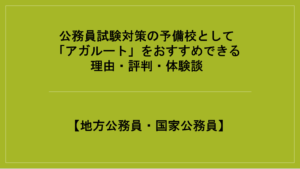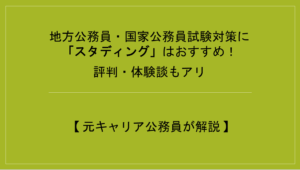このサイトで特に好評を頂いている記事の一つに以下のものがあります。

今回は、この記事の都道府県版になります。
筆者は地方公務員と国家公務員の実務をいずれも経験しておりますが、それでも、内容は飽くまで主観的にならざるを得ませんので、ご了承いただける方は、ぜひご覧ください。
注意事項
お決まりですが、最初に注意事項を述べさせていただきます。
都道府県職員の忙しさを定量的に測るとすれば、残業時間や有給取得日数を用いることで比較は可能ですが、それだけをもって各役所の大変さの全てを比較することは出来ません。部署によっては、「労働時間は短いけれども質的には大変」といったところもあるからです。
そういった意味では、部署の仕事を比較してランキング化するということは本質的には不可能です。常勤の公務員であれば、どの仕事を任せられることになってもそれなりに大変なことがあります。それでも、あえて序列をつけるならば、以下のようになると考えます。
忙しさには「量的な忙しさ」と「質的な忙しさ」がありますが、市区町村と異なり、都道府県の場合は、量的に忙しい部署は質的にも忙しいことが多いです。したがって、この記事では、両者を総合して忙しさを比較します。
なお、定性的な比較をするという性質上、主観的にならざるを得ない記事となりますので、ご承知おきの上、一参考に留めていただければと思います。
忙しい部署TOP5
まず、忙しい部署として、次の5つが挙げられます。
- 財政
- 人事
- 国の機関への出向
- 政策企画
- 教育委員会事務局
具体的に一つずつ見ていきます。
財政
仕事量や拘束時間という観点から最も忙しいと考えるのは、財政関係の部署です。市区町村のランキングでも財政課を筆頭にしましたが、それは都道府県においても同じです。とにかく絶対的な業務量が多く、忙しいです。
都道府県によって組織体系は異なりますが、ここでいう財政課とは、具体的には以下のような課をイメージしています。
- 東京都における財務局主計部の各課
- 大阪府における財務部財政課
他の課に配当する予算額を決定する立場にあるので、庁内では大きな裁量を持つことになります。露骨な言い方をすれば、各課の「カネを握っている」のが財政課です。
財政担当部署から各部局課へ予算額の査定等の仕事を振ることになりますが、これらの最終意思決定機関の都合によりその締切は非常にタイトに設定せざるを得ないということが多く、窮屈になりがちです。
この財政担当部署の窮屈さは、首長や議会との距離の地価さに起因します。首長や議会の近くで働けることは地方公務員としてのキャリア形成には良いですが、悪く言えばトップや議会の方針に振り回されることになります。
しいて言えば予算特別委員会の直前が繁忙期ですが、決算や予算編成の業務は通年に渡っているため、一年中忙しいイメージです。これらの繁忙期には、土日出勤やかなり遅い時間までの残業を余儀なくされます。
一か月あたりの超過勤務が45時間を超えることはザラで、80時間を超えるような人もそこそこ居る印象があります。
一方で、出世頭・花形部署の筆頭といったイメージもあります。財政や人事の出身は、庁内でも一目置かれる雰囲気があります。
人事課
次いで、人事関係の部署です。ここでいう人事課とは、具体的には以下のような部署をイメージしています。
- 東京都における総務局人事部人事課
- 東京都におけるその他各局の人事担当
- 大阪府における総務部人事課
財政担当部署に対して、人事担当部署では忙しさに波があるという特徴があります。自治体は基本的に4月1日付けで異動するため、その直前の1〜3月頃には特に業務が集中します。
また、一口に人事と言ってもその担当は細分化されており、異動、採用、服務、給与、研修といったものがあります。この中で最も忙しいのは異動担当で、次いで採用担当、服務担当が激務の印象です。
異動担当であれば、内示を出す日に向けて職員の配置を決めなければなりませんが、ギリギリまで各原課長から要望が入ったり、退職者が生じたり、内定辞退が生じたりするなどしてしまい、スケジュールに追われる日々となります。無理難題の板挟みの中で調整を強いられることが多く、量的・質的ともにタフな仕事です。
一方、「人事部」や「人事課」の中に、研修や労務の担当が置かれることもありますが、これらの担当は、比較的マイルドな印象です。
国の機関への出向
続いて、3番目は、国の機関への出向です。
「出向」というと悪いイメージを抱かれる場合もありますが、基本的に、国の機関への出向は期待への裏返しです。
ただ、東京霞が関の中央官庁に派遣される場合は、相当なハードワークを経験せざるを得ないことが多いです。
派遣先として多いのは、寄せ集め集団である内閣官房ですが、それ以外の府省庁においても都道府県との交流ポストが多く置かれています。
ただ、あくまで出向者として派遣される形になるので、プロパー職員ほどの業務量は要求されないといった声もあります。私は中央官庁に勤めていた際、都道府県から出向でいらっしゃった方と一緒に業務をしていた経験がありますが、これは実感としても感じるところです。
その点を踏まえて、財政と人事に次ぐ三番手くらいの忙しさだと考えています。
政策企画
続いて、4番目は、政策を担当する部署です。自治体によって名称が様々ですが、主に以下の部署を想定しています。
- 東京都における政策企画局政策部の各課
- 大阪府における政策企画部
忙しい理由は、ステークホルダーの「調整」が多いことにあります。当該自治体内の各部局課、国、市区町村、首長、議会、といった様々なステークホルダーと調整する事項がとにかく多いことから、激務に陥りがちです。
ちなみに、ここまでに紹介した課はすべて自治体の中では出世頭ですが、特に政策企画担当部署は花形の印象があります。激務には違いありませんが、期待の裏返しとも捉えられます。
一方で、激務の度合いとしては、財政や人事とは一線を画しており、比較的落ち着いている印象があります。(いずれにせよ自治体全体で見ればかなり忙しい方ではあります。)
教育委員会事務局
5番目は、都道府県教育委員会事務局です。
あまり注目されることは少ないですが、教育委員会事務局のうち、特に教職員の人事を扱う部署は、かなり忙しいです。
公立学校の教職員の人事体系はとにかく複雑です。基本的には、都道府県教育委員会、市区町村教育委員会、学校長の三者に権限が跨っており、煩雑な運用がされています。(アカデミックからも、二重行政であるとして指摘されているところです。)
さらに、都道府県の行政職員と学校職員の間で、制度が共通しているところもあればそうでないところもあるなど、複雑さを極めた制度となっています。
これらの事情から、市区町村教育委員会や学校長、当該都道府県の人事担当部署等のステークホルダーと連携しながら、タイトな期間で意思決定を行っていく必要に迫られるのです。
ホワイトな部署TOP7
続いて、定量的にホワイト寄りな部署は、次の8つです。
- 出先機関(福祉現場を除く)
- 監査委員会事務局
- 労働委員会事務局
- 収用委員会事務局
- 会計管理局
- スポーツ推進
- 環境保全
- 公園管理
これらを一つずつ具体的に見ていきます。
出先機関(福祉現場を除く)
まず、最もホワイトと言えるのは、各出先機関です。
具体的な名称は挙げだすときりがありませんが、「〇〇センター」「〇〇事務所」の名前で置かれているような、各局・各部の出先機関のことをイメージしています。そのほか、公立小中学校の事務職員や、都道府県が運用している職員研修所等も含みます。
本庁に比べて、絶対的な業務量がとにかく少ないです。
新規採用の直後に、これらの出先機関に一度は配置されることが多いです。年齢を重ねてから出先機関に長く配属されている人は、出世よりもプライベートを充実させたいと割り切っている人が多い印象です。
一方で、住民と直接的に接する可能性は本庁よりも高まるため、質的にホワイトといえるかどうかは、出先機関によっても変わってきます。
こういった理由から、全ての出先機関がホワイトとは言い切れません。たとえば、都道府県の児童相談所については、住民の極めてハードなシチュエーションに切り込んでいく必要があるため、出先機関ではありますが、ホワイトとはいえないと考えます。
監査委員事務局
次いで、監査委員事務局です。
地方自治法に定められた機関である「監査委員」の下、自治体の内部監査を行います。仕事の相手方が内部になるという特徴があります。
監査といっても結局は身内に対して行うものであり、量的・質的にもホワイトな印象があります。ただし、その分自治体の人事リソースを多量に割くようなものでもありませんので、ポストは少なく、配属される可能性は小さいといえます。
特に規模の大きな自治体であるほど、配属されることは珍しいです。
労働委員会事務局
続いて、3番目は、労働委員会事務局です。
こちらも、地方自治法に根拠を持つ労働委員会の事務を行うための事務局です。
広域自治体に置かれる委員会の事務局は、上掲の教育委員会事務局だけは激務に陥ることが多い一方で、それ以外は基本的にホワイトな印象が強いです。
ただし、監査委員事務局と同様に、ポスト数は限定的です。
収用委員会事務局
続いて、4番目は、収用委員会事務局です。
土地の収用等に係る事務がメインですが、現代の収用委員会は、職場として考えた時には基本的にホワイトです。
かつての成田空港のような、大規模な収用の問題が発生しない限り、ホワイトといってよいと考えます。
会計管理局
続いて、5番目は、会計管理局です。
定型的な業務が多く、量的にも定時でさばけるくらいの業務量であることが多いです。
その理由は、どこまで厳しく審査するかといった大きな裁量が与えられている点に起因します。他部署からの指示を受けることは少ないので、仕事の量・質を自ら決定しやすい立場にあるといえます。
監査委員会事務局にも通じるところがありますが、特定の領域の政策を扱うわけではなく、会計処理に徹することになるので、役所の中で少し浮世離れした存在です。
文化・スポーツ推進
続いて、6番目は、文化・スポーツ推進関係の部署です。
具体的には、以下のような部署のことをイメージしています。
- 東京都におけるスポーツ推進本部内の各部課
- 大阪府における府民文化部文化・スポーツ室の各課
スポーツ推進のほか、生涯学習の事務等を行う部署もここに含んでいます。
本庁に置かれる事務の中では、批判の対象になることが少ない政策領域であること、制度の改変のスピードが落ち着いていることなどから、比較的業務がマイルドです。
環境保全
続いて、7番目は、環境保全関係の部署です。
具体的には、以下のような部署をイメージしています。
- 東京都における環境局自然環境部、資源循環推進部の各課
以上のような、「自然」や「エネルギー」の側面から見た環境行政は、文化・スポーツ推進と同様の理由から、業務は比較的落ち着いている印象です。
ただし、都道府県におかれる公害の規制や補償の関係の部署については、「環境」の名が付く部局の中に置かれることがありますが、そこそこシビア・ハードな案件に直面する可能性もあるため、ホワイトかと問われると疑問です。
公園管理
最後に、公園管理関係の部署です。
たとえば、以下のような部署です。
- 東京都における建設局公園緑地部の各課
- 大阪府における都市整備部公園課
これらの部署の扱う業務は、本庁の業務の中では比較的自律的であるという特徴があります。
住民からクレームが入ることはありますが、基本的には当該部署の決めたスケジュールどおりに業務を進められる案件が多いため、量的にはある程度落ち着いているといえます。
受験生の方へのおすすめ記事等
以上です。
自治体の受験生の方へは、以下の記事等もおすすめできますので、よろしければご覧ください。